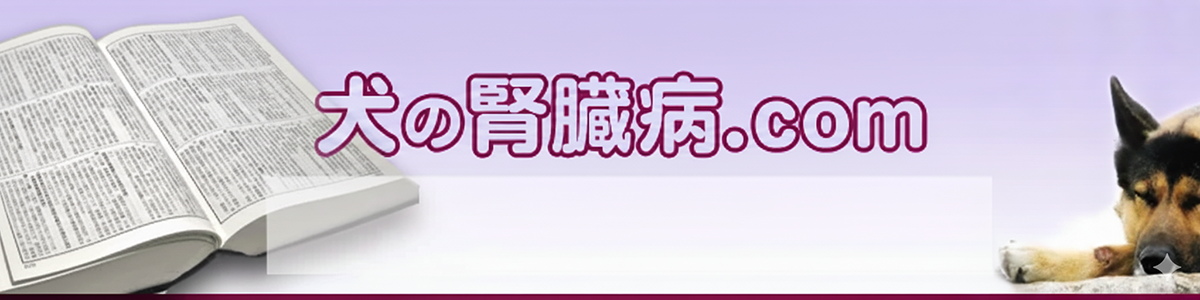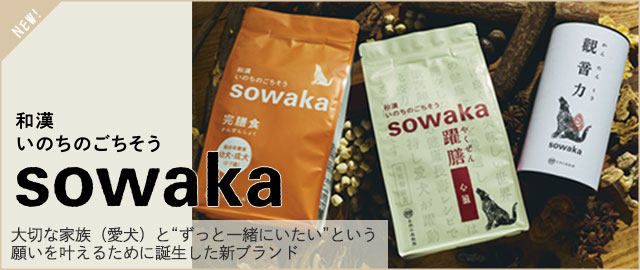Contents
腎臓病は「ステージごとの管理」が寿命を左右する
犬の腎臓病は、進行具合によってステージ分類されます。
この分類は国際獣医腎臓学会(IRIS)の基準をもとに、血液検査(クレアチニン・SDMA)や尿検査の結果で判断されます。
結論として、どのステージにあるかを知ることは、その後の治療方針や食事管理を決めるための最重要情報です。
「まだ初期だから予防に力を入れる」「進行しているから点滴が必要」など、ステージによって対策が大きく変わります。
犬の腎臓病ステージ分類とは?
基準となる検査項目
-
クレアチニン(Cre):血液に残る老廃物の量を示す
-
SDMA:早期に腎臓の機能低下を検出できる新しいマーカー
-
尿比重・蛋白尿:尿を濃縮できているか、タンパク質が漏れていないか
これらを総合的に判断して、ステージI~IVに分類されます。
犬の腎臓病ステージごとの特徴と症状
ステージ I(ごく初期)
-
クレアチニン:1.4以下
-
SDMA:14未満
-
ほぼ無症状で、日常生活に変化は見られない
-
偶然の健康診断や尿検査で異常が見つかるケースが多い
👉 この段階で発見できれば、寿命を大きく延ばせる可能性が高い。
ステージ II(初期~軽度)
-
クレアチニン:1.4〜2.0
-
SDMA:14〜25
-
多飲多尿が見られる
-
食欲が落ち始める
-
毛づやが悪くなり体重減少も
👉 食事療法を開始するタイミング。療法食の導入で進行を遅らせられます。
ステージ III(中等度)
-
クレアチニン:2.1〜5.0
-
SDMA:26〜38
-
嘔吐や下痢、口臭、食欲不振など臨床症状が明確に出てくる
-
尿が薄くなり、体に毒素が溜まりやすい
👉 薬物治療・点滴・サプリメントなど、食事だけでなく医療的管理が必要。
ステージ IV(重度)
-
クレアチニン:5.0以上
-
SDMA:38以上
-
食欲廃絶、嘔吐、痙攣、極度の体重減少など末期症状が見られる
-
尿毒症により命の危険が迫る
👉 この段階では延命と苦痛緩和が治療の中心になります。
ステージ別の治療と食事管理
ステージ I・II(早期)
-
定期的な血液・尿検査
-
腎臓療法食への切り替え
-
水分摂取を促す工夫(ウェットフード、スープ)
👉 「早期発見=進行を遅らせる最大のチャンス」です。
ステージ III(中期)
-
食事療法+薬物治療(ACE阻害薬、リン吸着剤など)
-
皮下輸液(点滴)で水分補給
-
食欲不振に対しては食欲増進剤を使用する場合も
ステージ IV(末期)
-
点滴・投薬で症状を和らげる
-
栄養補給を工夫しながら「QOL(生活の質)」を維持
-
飼い主と獣医が話し合い「どの治療を優先するか」を決める段階
飼い主がすべきこと(ステージ別)
-
I・II期:半年〜1年ごとの検査を徹底し、日常観察を欠かさない
-
III期:症状をメモし、すぐ獣医に報告できるようにする
-
IV期:犬の生活の質を第一に考え、無理な延命ではなく「快適に過ごせる時間」を重視する
よくあるQ&A
Q. うちの犬はステージIIですが、どれくらい生きられますか?
→ 個体差がありますが、療法食+治療で数年以上元気に過ごす犬も多いです。
Q. ステージIIIになったらもう手遅れですか?
→ 手遅れではありません。治療と点滴で進行を遅らせ、症状を和らげることは可能です。
Q. ステージIVになったらどうすれば?
→ 苦痛を和らげるケアが中心となります。獣医と相談して「愛犬にとって最善の選択」を考えることが大切です。
腎臓病はステージを知って対策することが大切
-
腎臓病はステージ分類で治療方針が決まる病気
-
早期(I・II期)なら進行を遅らせられる可能性が高い
-
中期以降(III・IV期)は治療とケアで「生活の質」を守ることが重要
👉 愛犬の検査数値と症状を正しく理解し、ステージに合ったケアを続けることが寿命を延ばす鍵です。
まとめ
-
犬の腎臓病はI〜IV期にステージ分類される
-
基準はクレアチニン、SDMA、尿検査の結果
-
ステージごとに治療方針が変わる
-
早期なら食事療法で進行を遅らせられる
-
中期以降は点滴や薬物治療も必要
-
飼い主は「検査・観察・相談」を継続することが重要