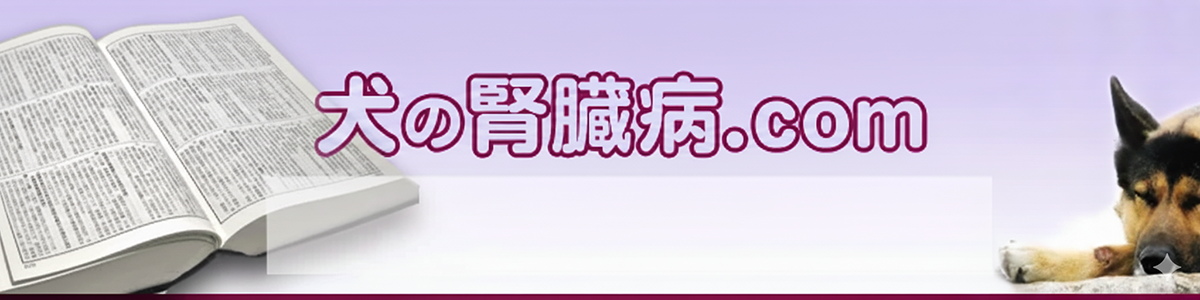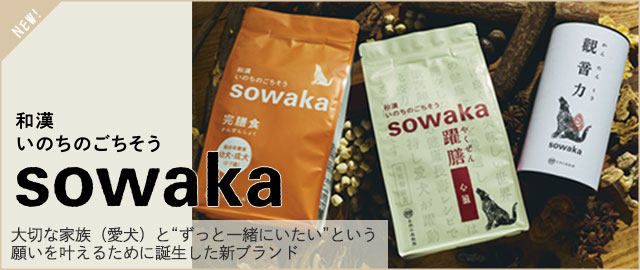愛犬が腎臓病と診断されると、毎日の生活でできるケアを探す飼い主さんも多いでしょう。
その中でも「マッサージ」は、血流改善やリラックス効果が期待できるサポート方法です。
しかし、やり方を間違えると体に負担をかける危険もあります。
本記事では、腎臓病の犬に安全に行えるマッサージ方法と注意点を詳しく解説します。
Contents
腎臓病の犬にマッサージをしても大丈夫?
正しく行えば健康維持に役立つ
腎臓病の犬でも、適切なマッサージは血流促進やストレス軽減に効果的です。
腎臓病は血液中の老廃物をうまくろ過できなくなる病気で、代謝が低下しやすい状態。
血行が悪くなると、老廃物が体内に溜まり、倦怠感や食欲不振の悪化を招くことがあります。
マッサージで血流を改善することで、体内循環がスムーズになり、腎臓の負担を軽くするサポートになります。
✅ 重要ポイント
軽い刺激で全身の代謝を促す
ストレスを緩和しリラックス効果を高める
強く押す・長時間やるのはNG
腎臓病の犬にマッサージを行うメリット
① 血流・リンパの流れを促進
腎臓は血液をろ過して老廃物を排出する臓器です。
血流が滞ると腎臓の働きも悪化するため、マッサージによって循環をサポートすることが重要です。
背中や肩、腰などの筋肉をやさしくなでるだけで、血液とリンパの流れが改善し、体の冷えやむくみを防ぐことができます。
② リラックスしてストレスを軽減
腎臓病の犬は慢性的な倦怠感や不安感を抱えがちです。
飼い主の温かい手で触れられることで、安心感が生まれ、副交感神経が優位になりリラックス状態になります。
マッサージは、薬や食事では得られない「心のケア」としても効果的です。
③ 飼い主との絆を深める
マッサージの時間は、愛犬にとって「安心できる触れ合いの時間」。
飼い主が優しく声をかけながら触れることで、犬は心を落ち着け、信頼関係をより深めることができます。
マッサージをする際の注意点
体調が悪い日は控える
嘔吐や下痢、脱水、発熱などがある日はマッサージを避けましょう。
腎臓病の進行度によっては、体に刺激を与えることで逆効果になることもあります。
不安な場合は、事前に獣医師へ相談しましょう。
力加減は「なでるように」が基本
マッサージの圧は「毛並みを整えるように軽くなでる」程度で十分です。
強く押したり揉んだりすると筋肉や内臓に負担がかかります。
✅ 避けるべきNGマッサージ
指圧や揉み解し(腎臓に負担)
背中中央の強い圧迫(腎臓の位置)
長時間のマッサージ(疲労を招く)
時間と頻度の目安
1回あたり 5〜10分以内 を目安に、1日1〜2回行いましょう。
短時間でも続けることで、徐々に代謝や気分が安定します。
部位別おすすめマッサージ方法
| 部位 | 方法 | 効果 |
|---|---|---|
| 首・肩 | 指の腹で円を描くように軽く撫でる | 血行促進、筋肉のこり改善 |
| 背中 | 手のひらで大きくなでる | リラックス効果、体温維持 |
| 腰 | 手を温めて軽く当てる | 腎臓周囲の血流サポート |
| 足先 | 軽くさするように撫でる | 冷え・むくみの予防 |
💡 ポイント:腎臓付近は直接押さない!
背中の中央〜腰の少し上にある腎臓を刺激しすぎると逆効果になるため注意。
マッサージと併用したいケア
温熱ケア(ホットタオル)
腎臓病の犬は血行が悪く冷えやすい体質。
マッサージ前に温かいタオルを腰に5分ほど当てると、筋肉が緩みマッサージ効果が高まります。
アロマやハーブを活用
犬に安全なラベンダーやカモミールのアロマを使うと、よりリラックス効果を高められます。
ただし**精油の濃度は非常に薄く(1滴を水で100倍程度)**し、直接皮膚につけないようにしましょう。
水分補給を忘れずに
マッサージ後は血流が促進されるため、水分補給が重要です。
新鮮な常温の水を与え、尿量や色の変化も観察してください。
マッサージができないときの代替ケア
・温めたタオルで全身を包む
・やさしく撫でながら声をかける
・室内で軽く歩かせる
これらも立派な「触れ合いマッサージ」。
無理せず、愛犬のリズムに合わせて行いましょう。
まとめ
腎臓病の犬にとって、マッサージは体と心の両面を支える自然なケア方法です。
ただし、やり方を誤ると体調を崩すこともあるため、「優しく・短時間・無理をしない」を守りましょう。
✅ この記事のまとめ
マッサージは血流促進・リラックスに有効
強い刺激や長時間はNG
1日5〜10分を目安に継続
体調変化を観察しながら行う
毎日の触れ合いの中で、少しでも愛犬が穏やかな時間を過ごせるよう、優しい手でサポートしてあげましょう。