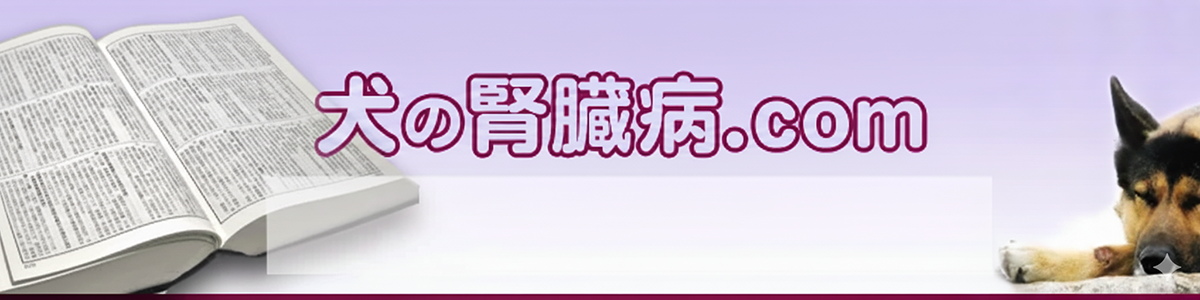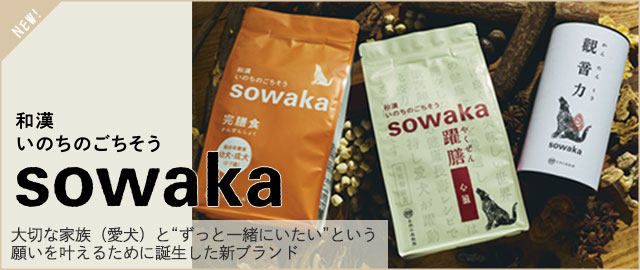Contents
早期発見が犬の寿命を大きく左右する
犬の腎臓病は、「沈黙の臓器」と呼ばれる腎臓がダメージを受けることで進行する病気です。腎臓は本来、血液をろ過して老廃物を排泄する働きを担っています。しかし、その機能が失われても犬は初期段階ではほとんど症状を見せません。
つまり、気づいたときにはすでに重度の腎不全に進行しているケースが多いのです。
だからこそ飼い主が「日常の小さな変化」に気づき、さらに定期的な検査を受けることが犬の命を守ります。早期発見・早期治療こそが寿命を延ばす最大のポイントです。
腎臓は一度壊れると元に戻らない臓器
腎臓の病気が厄介なのは、再生能力が非常に低いことにあります。肝臓はある程度ダメージから回復できますが、腎臓は壊れた部分を取り戻すことができません。そのため「いかに早く異変を見つけて進行を遅らせるか」が重要になります。
さらに、腎臓病は進行すると全身に影響を与えます。
-
老廃物が体にたまる(尿毒症) → 嘔吐・食欲不振・けいれんなどを引き起こす
-
電解質異常 → 心臓や神経に障害をもたらす
-
貧血 → 元気がなくなり、散歩もできなくなる
つまり、腎臓病は単なる「腎臓のトラブル」ではなく、犬の全身の健康を脅かす深刻な病気なのです。
日常で見逃してはいけないサイン
では、実際に飼い主が気をつけるべきサインとはどんなものかを整理してみましょう。
初期に現れることが多いサイン
-
水を飲む量が増える(多飲)
-
おしっこの量が増える(多尿)
-
食欲が落ちる
-
毛づやが悪くなる
-
少し痩せてきた
-
以前より寝ている時間が長い
特に「多飲・多尿」は、飼い主が家庭で気づきやすい変化です。
たとえば、1日に何度も水を足さないといけない、トイレシーツの交換が早くなったと感じたら要注意です。
中期以降で出てくる症状
-
嘔吐や下痢が増える
-
アンモニア臭のような口臭
-
ぐったりして動かない
-
尿の色が薄くなる、または逆に極端に濃くなる
こうした症状が見られたら、すぐに動物病院を受診する必要があります。
検査で腎臓の健康状態を確認する方法
犬の腎臓病を確定的に診断するには、動物病院での検査が不可欠です。
血液検査
-
BUN(尿素窒素):腎臓が老廃物を排泄できているかを確認
-
Cre(クレアチニン):腎機能の低下度を示す代表的な指標
-
SDMA:近年注目される早期発見マーカー。従来の検査では見つけにくい軽度の腎障害も検出可能
尿検査
-
尿比重:尿が薄い場合、腎臓が十分に濃縮機能を果たせていない可能性
-
蛋白尿:腎臓からタンパク質が漏れていると、進行性の腎障害の可能性が高い
画像診断
-
超音波(エコー)検査:腎臓の形や大きさを直接観察し、腫瘍や結石の有無も確認できる
定期健診の目安
-
健康な若い犬:年1回の血液・尿検査
-
シニア期(7歳以上):半年に1回の検査を推奨
飼い主ができる日常の工夫
検査だけでなく、家庭での観察と記録も早期発見に直結します。
日常でできる工夫
-
毎日の飲水量をメモする
-
尿の色・回数を観察する
-
体重を週1回チェック
-
ごはんを残す日が続かないか確認する
こうした小さなデータを病院で伝えることで、診断の精度が高まり、病気の進行具合もより正確に把握できます。
まとめ:小さな気づきと検査が犬を救う
まとめると、犬の腎臓病は「沈黙の病気」だからこそ飼い主の観察眼が命を救うと言えます。
-
多飲・多尿は最もわかりやすいサイン
-
血液検査・尿検査・エコー検査を定期的に受ける
-
日々の観察記録をつけて獣医師に伝える
この3つを実践すれば、腎臓病を早期に発見できる可能性は格段に高まります。
「少しの違和感に気づき、迷わず検査する」
これが、愛犬の寿命を延ばし、健康な生活を送らせるための最も確実な方法なのです。