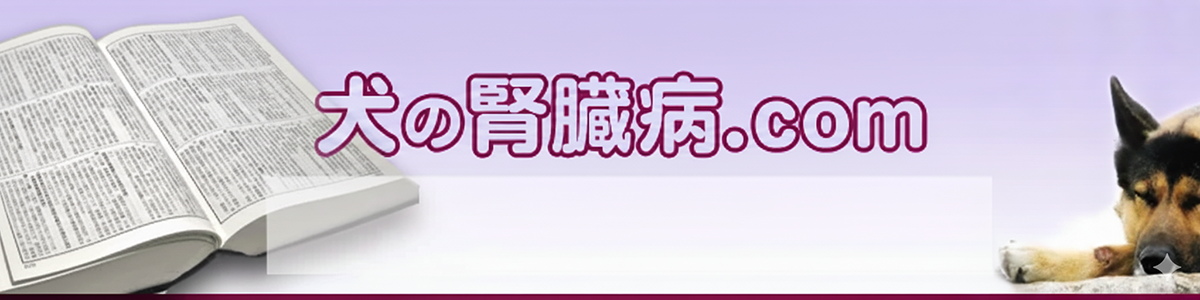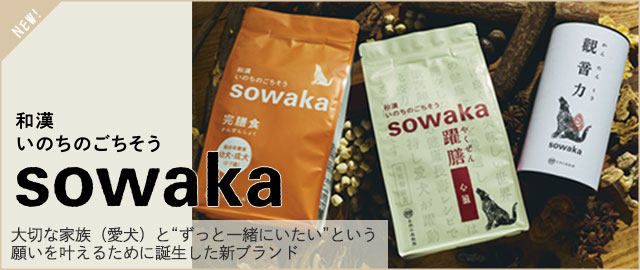Contents
腎臓病の犬がごはんを食べない…それはSOSのサインかも
愛犬が腎臓病を患っていて、急にごはんを食べなくなった…。
飼い主にとってこれほど心配なことはありません。
しかし、「食べない=わがまま」ではありません。
実は、腎臓病の進行や体内の変化によって食欲が低下しているケースがほとんどです。
この記事では、
-
腎臓病の犬が食べない主な原因
-
すぐできる食事の工夫と対処法
-
食べない時の危険サインと受診目安
を、わかりやすく解説します。
腎臓病の犬がごはんを食べない理由とは?主な原因5つ
💡Point
腎臓病の犬が食べないのは、身体の不調やフードの変化によるストレスが関係しています。
以下のような要因が重なっていることが多いです。
1. 尿毒症の進行による吐き気や倦怠感
腎臓の働きが低下すると、老廃物(尿毒素)が体内に溜まり、吐き気・だるさ・食欲低下を引き起こします。
これは「わがまま」ではなく、体の防御反応です。
特に「食べたがらない」「口をつけてすぐやめる」場合は、尿毒症の影響が疑われます。
2. 療法食の味や匂いに慣れない
腎臓病の療法食は、タンパク質や塩分を制限しているため、香りや風味が薄く、食いつきが悪くなりがちです。
嗅覚の敏感な犬にとって、「いつもの匂いがしない=食べ物ではない」と感じてしまうことも。
3. 脱水や口内炎による「食べる痛み」
腎臓病では口腔環境の悪化や口内炎を伴うことがあり、噛むと痛い・しみるといった状態になることがあります。
また、体の水分バランスが崩れると、口の乾燥やにおいが強くなり、さらに食欲が低下します。
4. 点滴や薬の影響による一時的な食欲低下
治療中の皮下点滴や投薬によって、吐き気やだるさが出ることがあります。
特に利尿剤・降圧剤・抗生物質などは、体調に影響することも。
ただし、これらは一時的なもので、体調が安定すれば回復する可能性が高いです。
5. 環境やストレスによる心理的要因
腎臓病は慢性疾患のため、体調変化や通院ストレスが積み重なります。
犬は環境の変化にも敏感なので、不安・孤独・痛みへの恐怖が「食欲低下」として現れることがあります。
すぐにできる!腎臓病の犬がごはんを食べない時の対処法
💡Point
焦らず、食べやすく・香りが立ち・安心できる工夫を試すのがポイントです。
1. フードを少し温めて香りを引き出す
腎臓病の療法食は味が淡泊。
電子レンジで5〜10秒程度温めることで香りが立ち、食欲を刺激できます。
ただし、熱くしすぎると栄養が壊れるので注意。
2. スープやゆで汁を少量加える
鶏むね肉や白身魚のゆで汁(塩分なし)をスプーン1〜2杯混ぜるだけで風味アップ。
同時に水分補給にもなります。
🐾ポイント:リンが多くならないよう、濃いスープは避けましょう。
3. 飼い主の手から少しずつ与える
愛犬は飼い主の存在に安心します。
「食べないから」と放置せず、スプーンや手のひらで優しく少量ずつ与えるのも効果的。
スキンシップによるリラックス効果も期待できます。
4. 少量を回数多く与える「分食」に切り替える
1日2食→4〜5回に分けて少しずつ与えると、胃腸への負担が減り、食べやすくなります。
また、匂いが立ちやすい新鮮な状態で出せるのもメリット。
5. フードの種類・形状を変えてみる
同じ療法食でもメーカーによって風味や質感が異なります。
たとえば:
-
ドライ→ウェットタイプに変える
-
ヒルズのk/d → ロイヤルカナンの腎臓サポートへ切り替え
味覚の好みが合えば、食欲が戻ることもあります。
それでも食べない時にできるサポート方法
💡Point
無理に食べさせず、体に負担の少ない方法を選ぶことが大切です。
1. 強制給餌は獣医師と相談して判断
食べさせたい気持ちは理解できますが、無理に口へ入れると誤嚥性肺炎のリスクがあります。
安全に行う場合は、必ず動物病院でやり方を教わるようにしましょう。
2. 液状フード・ペーストタイプの栄養食を利用
食べる力が落ちているときは、
-
a/d缶(ヒルズ)
-
クリニケア(森乳)
-
腎臓サポートリキッド(ロイヤルカナン)
などの流動食タイプがおすすめ。
スプーンやシリンジで無理なく与えられます。
3. サプリ・点滴で体調を整えて再挑戦
体調が悪化していると、そもそも「食べる力」が出ません。
まずは皮下点滴や腸内ケアサプリで体を整え、数日後に再度トライするのが現実的です。
食べない状態が続くと危険?すぐに病院へ行くべきサイン
次のような症状が見られたら、自己判断せず早急に受診しましょう。
-
3日以上まったく食べない
-
水もほとんど飲まない
-
嘔吐・口臭・ぐったりして動かない
-
尿の色が濃い・量が極端に減った
-
体重が短期間で減少
これらは腎不全の悪化や尿毒症のサインである可能性があります。
再び食べてくれるようにするための生活改善ポイント
食事の工夫だけでなく、環境の見直しも効果的です。
-
食器を清潔に保ち、金属臭を避ける(陶器・ガラス製が◎)
-
静かで落ち着いた環境で食事を用意
-
室温を20〜25℃に保ち、体を冷やさない
-
食後は「よく食べたね」と褒めて安心感を与える
-
水分補給をこまめに促す(ウェット多めOK)
🌿「食事は薬」ではなく「食事は癒し」として捉えることが、長く続ける秘訣です。
焦らず、愛犬のペースで食欲回復をサポートしよう
腎臓病の犬が食べないのは、体の不調や不安が原因であり、決して「わがまま」ではありません。
大切なのは、
-
焦らず少しずつ工夫を重ねること
-
必要に応じて獣医師と相談しながら進めること
-
愛犬が「食べたい」と思える環境を整えること
🐶 小さな一口が、明日の元気につながります。
飼い主さんの優しい手が、きっと愛犬の食欲を取り戻す力になります。