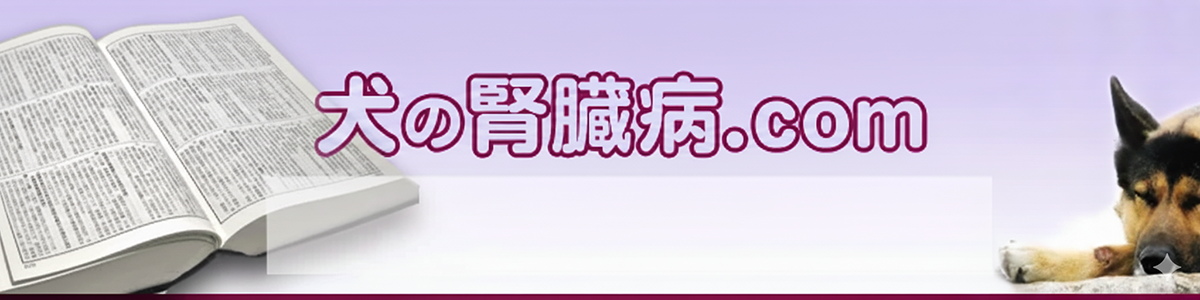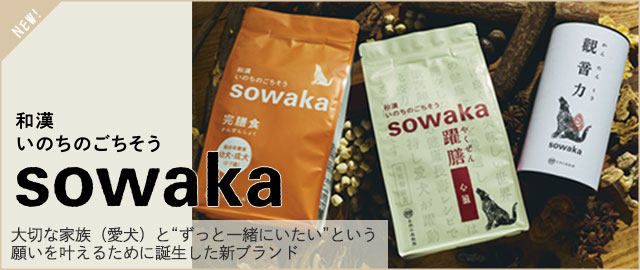犬の腎臓病はシニア期の発症が多く、一度進行すると元に戻すことが難しい病気です。早期発見と生活管理によって進行を遅らせることができるため、日々のケアがとても重要になります。この記事では、「犬の腎臓病における生活で気を付けるポイント」を、飼い主さん目線でわかりやすく解説します。
「犬 腎臓病 生活 気を付けること」というテーマでお探しの方に役立つよう、食事・水分・環境・運動・自宅ケアなど総合的にまとめています。
Contents
① 犬の腎臓病とは?原因と特徴
腎臓は血液中の老廃物をろ過し、尿として排出する重要な臓器です。腎臓病になるとこの機能が低下し、毒素が体内に溜まりやすくなります。
主な原因
-
加齢(7歳以上でリスク増加)
-
遺伝(小型犬や特定犬種で多い傾向)
-
慢性的な脱水
-
感染症
-
中毒(ブドウ・ユリ・薬剤など)
-
先天的な腎形成異常
急性腎不全は突然悪化するケースもありますが、慢性腎臓病は「気づいたときには進行している」ことも多いため、生活の見直しが重要になります。
② 初期症状と気づきにくいサイン
腎臓病の初期は「なんとなく元気がない」「食欲のムラがある」など、見逃しやすい症状が多くあります。
よくあるサイン
-
水をたくさん飲む(多飲)
-
尿の量が増える(多尿)
-
口臭がきつくなる(アンモニア臭)
-
食欲低下
-
体重減少
-
嘔吐・下痢
「シニア犬の変化かな?」と見過ごしてしまうケースもあるため、定期的な血液検査・尿検査が不可欠です。
③ 腎臓病の犬が生活で気を付けること
ここからが本題です。「生活で気を付けること」は、大きく分けると以下の6つになります。
✅1. 食事管理(療法食・手作り食・水分量)
腎臓病の犬にとって食事は最重要ポイントです。
-
低たんぱく・低リン・低ナトリウムの療法食が基本
-
高品質なたんぱく源(卵・白身魚など)
-
療法食を嫌がる場合はふやかす・温める・トッピングするなど工夫
-
手作り食を考える場合は獣医師と相談必須
-
ウェットフードやスープで水分も補給できる
「おやつはダメ?」とよく聞かれますが、市販のおやつの多くは塩分・たんぱく質が高めなので注意が必要です。腎臓病用のおやつや、キャベツ・かぼちゃなど低リン野菜が安心です。
✅2. 水分摂取と脱水対策
腎臓病では尿が薄くなりやすく、脱水になりやすい状態です。
-
いつでも飲めるよう複数箇所に水を設置
-
電動給水器や浅めの器で飲みやすく
-
ウェットフード・ヤギミルク・スープで水分補助
-
冬や夏の室内湿度も重要
脱水は症状を一気に悪化させるため、日々の観察が大切です。
✅3. 運動・散歩の調整
体力を維持することは重要ですが、無理は禁物。
-
激しい運動や長距離散歩は避ける
-
体調に合わせて回数を調整
-
真夏・真冬は気温管理を徹底
-
元気なときでも「少し物足りないくらい」でやめる
腎臓病の犬は疲れやすく、回復に時間がかかる傾向があります。
✅4. ストレスを減らす生活環境
ストレスは腎臓や免疫にも影響します。
-
静かな休息スペースを確保
-
温度・湿度を一定に(夏はエアコン、冬は冷え対策)
-
床は滑りにくく、寝床は清潔に
-
留守番が多い場合は見守りカメラも検討
生活リズムを大きく変えないこともポイントです。
✅5. 自宅ケア・サプリ・皮下点滴
ステージや症状によっては、自宅での補液やサプリ管理も必要になります。
-
獣医師の指示で皮下点滴(慢性腎不全でよく使われる)
-
リン吸着剤・血圧の薬・胃薬などを併用するケースも
-
オメガ3脂肪酸、プロバイオティクス、活性炭サプリなどが選択肢に
「飲ませ忘れ」や「嫌がって吐き出す」などもよくあるので、家族で役割を決めておくと安心です。
✅6. おやつ・嗜好品の注意点
よくある落とし穴が「気休めに与えるおやつ」「人間の食べ物」です。
-
肉・チーズ・魚などはリンとたんぱく質が多い
-
ジャーキーやボーロも意外と添加物が多い
-
塩分は腎臓に負担がかかる
-
与えるなら療法食トッピングや野菜系を
「かわいそうだからあげたい」という気持ちが、結果的に病気を悪化させることもあります。
④ 定期検査と数値管理の重要性
腎臓病は進行性のため、「定期検査=延命ケア」です。
よく使われる検査項目
-
クレアチニン
-
BUN(尿素窒素)
-
SDMA(早期発見に役立つ)
-
尿比重
-
タンパク尿
ステージによって検査頻度は異なりますが、進行防止には「数値の変化を早く察知すること」が不可欠です。
⑤ 飼い主が見逃しやすい危険サイン
以下のような変化があればすぐに受診が必要です。
-
急な食欲低下
-
嘔吐や下痢
-
水を飲まなくなる
-
逆に異常な多飲
-
尿が極端に減る・出ていない
-
ぐったりして動かない
-
口臭や貧血症状
腎臓は静かに悪化する臓器のため、「なんとなく変」を放置しないことが大事です。
⑥ 進行を遅らせ、穏やかに暮らすために
犬の腎臓病は完全な治癒は難しいものの、生活管理次第で寿命やQOLは大きく変わります。
✅ 食事管理(低たんぱく・低リン)
✅ 脱水防止と水分補給
✅ 疲れにくい生活リズム
✅ ストレスの少ない環境
✅ サプリ・薬・補液の併用
✅ 定期検査と小さな変化のチェック
これらを続けることで、進行を遅らせ「その子らしい日常」を保つことが可能です。
腎臓病と診断されても、悲観する必要はありません。正しい知識とケアで、穏やかな生活を長く続けていくことができます。