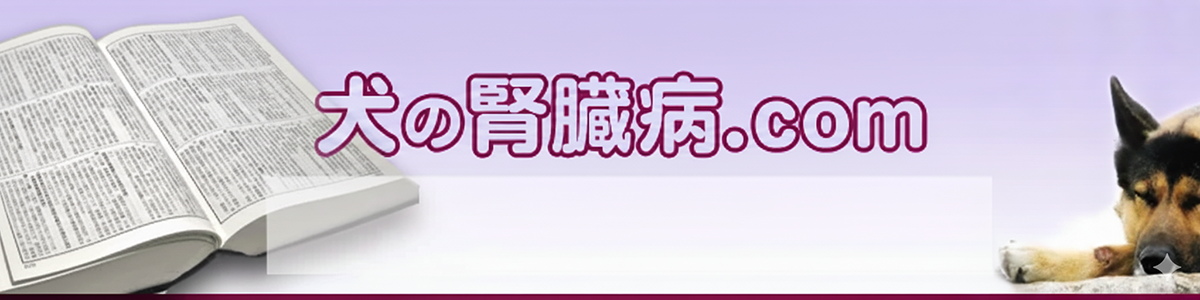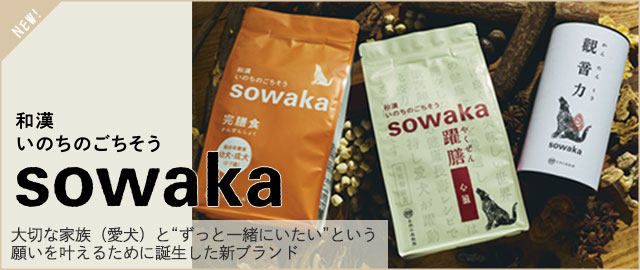Contents
腎臓病の犬にとって「寒さ」は大敵
腎臓病を患っている犬は、体温調整機能が低下しているため、寒さの影響を受けやすくなっています。
特に冬場は血流が悪くなり、腎臓への負担が増すことも。
「冷え」は腎臓病の進行を早める要因の一つ。
この記事では、寒さが腎臓病に与える影響と、今日からできる具体的な寒さ対策を解説します。
愛犬が冬を穏やかに過ごせるよう、しっかり備えてあげましょう。
なぜ腎臓病の犬は寒さに弱いのか?
💡Point
腎臓病の犬は、代謝の低下・筋肉減少・血流の悪化により、冷えやすくなっています。
1. 体温を作る「筋肉量」が減る
腎臓病になると、タンパク質制限や代謝低下によって筋肉量が落ちやすくなります。
筋肉は「体を温める器官」。そのため、体内で熱を作る力が弱まり、冷えを感じやすくなります。
2. 血流が悪くなり、末端が冷える
腎機能が落ちると、血液循環にも影響が出ます。
特に手足の先・耳・尻尾など末端の血行が悪くなり、体温が下がる原因に。
これにより、内臓への酸素供給も減少し、腎臓への負担がさらに増すことがあります。
3. 免疫力が低下し、風邪や体調不良を起こしやすい
腎臓病の犬は体力が落ち、免疫力も低下しています。
冷えが続くと免疫バランスが崩れ、感染症や体調悪化を招くリスクが上がります。
腎臓病の犬にできる5つの寒さ対策
💡Point
「温めすぎず、冷やさない」ことが基本です。
体温を一定に保つ工夫が、腎臓への負担を軽減します。
1. 室温は20〜25℃をキープ
寒暖差が大きいと体調を崩しやすいため、一定の室温管理が重要です。
理想は20〜25℃、湿度は40〜60%。
エアコンを使う場合は、直接風が当たらないように調整しましょう。
💡サーキュレーターで空気を循環させると温度ムラを防げます。
2. ベッド・毛布で下から温める
床からの冷気は体温を奪います。
ふかふかのベッドや毛布を敷き、体の下に断熱層を作ることが大切です。
特におすすめなのは:
-
低反発マット+フリース毛布の組み合わせ
-
冷たいフローリングの上にはカーペットやジョイントマット
🐾犬の寝床は「少し沈み込むくらい」がベスト。体圧分散で関節も保護できます。
3. 低温ヒーター・湯たんぽで局所的に温める
電気カーペットやペット用ヒーターを使う際は、低温やけどに注意。
直接肌に当てず、毛布越しに温めるのが安全です。
湯たんぽを使う場合は:
-
40℃前後のお湯を使用
-
タオルで包んでベッドの端に置く
-
愛犬が「自分で移動できる位置」に置く
4. 散歩は日中の暖かい時間帯に
朝晩の冷え込みは腎臓に負担をかけます。
散歩は10時〜15時の間の暖かい時間を選びましょう。
また、冬の地面は冷たいので、
防寒ウェアやドッグブーツを活用すると足元の冷え対策にも効果的です。
5. 食事と水分で「内側から」温める
寒い時期は、体を温める食材やぬるま湯を取り入れるのもおすすめです。
-
食事は常温〜人肌程度に温める(香りも立って食欲UP)
-
冷たい水ではなく、ぬるめの白湯を与える
-
ショウガ・鶏肉・かぼちゃなど「温性食材」は少量ならOK(ただし獣医に相談)
🍲腎臓に負担をかけないよう、「温かく・薄味・水分多め」が理想。
冷えによる体調変化に注意すべきサイン
以下のような様子が見られたら、体が冷えているサインかもしれません。
-
手足・耳・お腹が冷たい
-
震える・丸まって寝る時間が増えた
-
元気・食欲が落ちた
-
尿の量や色がいつもと違う
冷えによって血流が悪化し、腎臓の働きが低下することもあるため、早めの対処が必要です。
温めることは「腎臓を守るケア」
腎臓病の犬にとって、寒さ対策は体を守るための基本ケアです。
暖房器具や食事、散歩時間を工夫するだけで、冬の負担を大きく減らせます。
体を温めることは、「腎臓を守ること」。
愛犬が寒さを感じず、穏やかに冬を過ごせるように、
日々の生活環境を少しずつ整えてあげましょう。