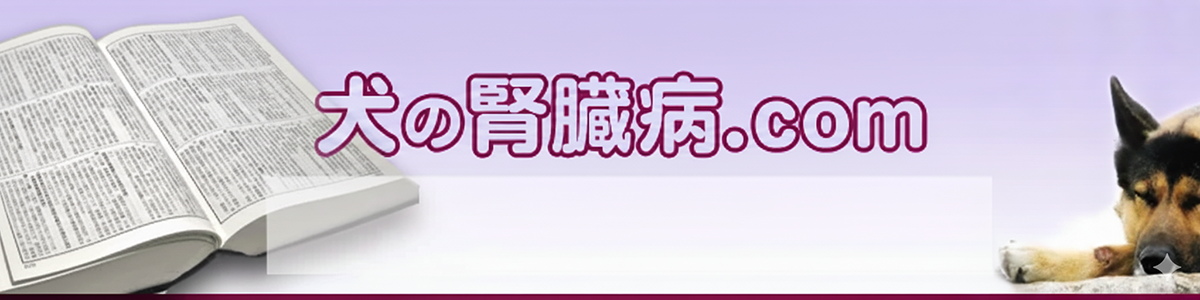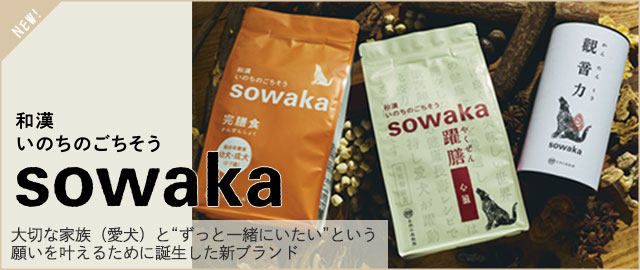犬の腎臓病は進行性の病気であり、腎機能の低下は体全体に影響を及ぼします。その中でも「神経疾患」との関係は見逃せません。腎臓が老廃物を排泄できなくなると、体内に毒素が蓄積し、脳や神経に悪影響を与えることがあります。さらに、神経疾患による代謝異常や循環障害が腎臓病を悪化させるケースもあります。本記事では犬の腎臓病と神経疾患の関係、合併症、ケアについて詳しく解説します。
Contents
腎臓病が神経に与える影響
-
尿毒症性脳症:腎不全末期に毒素が脳に作用し、けいれんや意識障害を引き起こす
-
末梢神経障害:老廃物の蓄積により神経伝達が乱れ、歩行異常やふらつきが出る
-
高血圧性脳症:腎臓病に伴う高血圧が脳の血管に影響し、けいれんや失明を招く
-
電解質異常(ナトリウム・カリウムのバランス異常):神経や筋肉の働きに影響し、脱力や不整脈が出る
神経疾患が腎臓に与える影響
-
てんかんやけいれん発作による一時的な酸素不足が腎臓の血流に影響
-
脊髄疾患や麻痺により排尿障害が起こり、膀胱炎や腎盂腎炎につながる
-
神経変性疾患による食欲低下や活動性低下で栄養不足が進み、腎臓の修復力を低下させる
腎臓病と神経疾患の代表的な合併症
-
尿毒症性脳症
-
高血圧性脳症
-
腎盂腎炎に伴う脊髄症状
-
慢性腎不全によるけいれん発作
合併症の症状
-
けいれん、ふらつき、失神
-
意識の混濁、反応が鈍い
-
歩行異常、立ち上がりにくい
-
排尿障害(尿失禁・排尿困難)
-
異常な鳴き声や行動の変化
管理とケアの方法
食事管理
-
腎臓病用療法食を基本とし、低リン・低ナトリウムを維持
-
電解質バランスを考慮した給餌が重要
-
消化しやすい形態に調整し、少量を複数回に分けて与える
薬物療法
-
腎臓病:降圧薬、制吐剤、リン吸着剤など
-
神経疾患:抗けいれん薬、鎮痛薬、炎症抑制薬
-
薬の排泄経路を考慮し、腎臓に負担をかけない薬剤を選択
水分補給
-
脱水予防のため常に新鮮な水を与える
-
嘔吐や下痢がある場合は皮下輸液で補助
定期的な検査
-
血液検査:BUN、クレアチニン、SDMA、電解質
-
血圧測定:高血圧の有無を確認
-
神経検査:反射、歩行、姿勢反応などをチェック
生活環境
-
転倒防止のため滑りにくい床を用意
-
トイレを近くに設置し、排尿しやすい環境を整える
-
ストレスの少ない生活リズムを維持
飼い主がよく抱く質問
腎臓病によるけいれんは治りますか?
一時的に薬で抑えることは可能ですが、根本的には腎臓病の管理が必要です。
神経疾患と腎臓病、どちらを優先して治療すべきですか?
命に関わる症状を優先します。例えば、けいれんが続く場合は神経系の治療を優先し、腎臓病の管理は並行して行います。
自宅で注意すべきことは?
けいれんや歩行異常がある犬は転倒防止、排尿管理、脱水予防を徹底してください。
まとめ
犬の腎臓病と神経疾患は互いに影響を与え合い、合併すると症状が重くなり治療が複雑化します。
-
腎臓病は尿毒素や高血圧により脳・神経に悪影響を与える
-
神経疾患は排尿障害や代謝異常を通じて腎臓病を悪化させる
-
管理は食事療法・薬物療法・水分補給・定期検査が基本
-
飼い主の観察と早期対応が合併症予防のカギ
腎臓と神経の両方に配慮したケアを続けることで、愛犬の健康寿命を守ることができます。