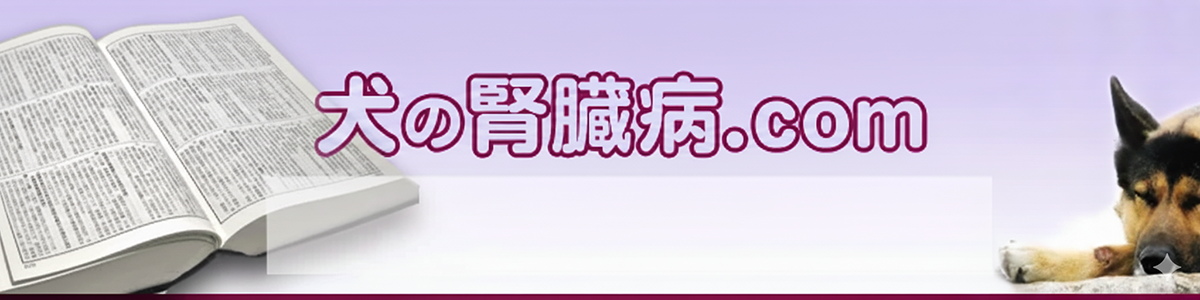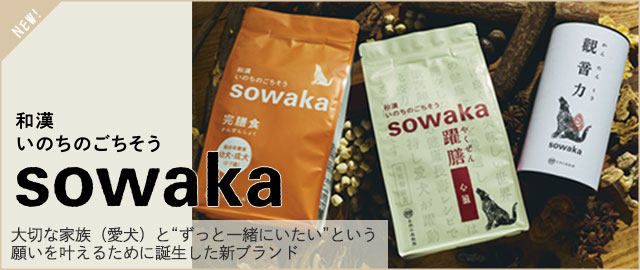犬の腎臓病は「サイレントキラー」と呼ばれるほど初期症状がわかりにくく、気づいたときにはすでに病気が進行していることが多い厄介な病気です。慢性腎臓病(CKD)は特に高齢犬に多く、早期に異変に気づくことが治療の成否を分けます。ここでは犬の腎臓病に見られる初期症状と、飼い主ができる早期発見のポイントを詳しく解説します。
Contents
犬の腎臓病の初期症状
多飲多尿
-
健康な犬の1日の飲水量は体重1kgあたり約50ml前後
-
例:体重10kgの犬 → 500ml程度
-
これを大きく超える場合は「多飲」
-
尿の量や回数も増加し、夜間にトイレに行きたがるケースもある
食欲不振
-
ご飯を残すことが増える
-
好物にも反応が鈍くなる
-
日ごとに食欲が減少していく
体重減少
-
フード量が変わらなくても体重が減る
-
筋肉が落ち、痩せて見える
口臭
-
アンモニア臭や独特のにおいがする
-
歯周病ではなく腎臓由来の可能性あり
元気の低下
-
散歩に行きたがらない
-
遊びへの関心が薄れる
-
眠っている時間が増える
これらは老化現象と間違われやすいですが、腎臓病の初期サインであることが少なくありません。
飼い主ができる早期発見のチェックポイント
飲水量・排尿量の記録
-
毎日の飲水量を測る
-
排尿の回数・量を観察する
-
急な増減があれば要注意
体重の定期測定
-
月1回以上、体重を記録する
-
徐々に体重が減少している場合は腎臓病を疑う
口臭・被毛の観察
-
口臭の変化は重要なサイン
-
被毛のツヤがなくなりパサつく場合も要注意
食欲の変化
-
「一時的な食欲不振」ではなく、「継続的な減退」が重要なサイン
動物病院での早期発見方法
血液検査
-
BUN(尿素窒素):上昇すると腎機能低下の可能性
-
クレアチニン:腎臓病の代表的指標
-
SDMA:近年注目されているマーカーで、クレアチニンより早期に異常を捉える
尿検査
-
尿比重:腎臓の濃縮力を確認
-
タンパク尿:腎障害の早期サイン
画像診断
-
超音波検査で腎臓の大きさや形態を確認
-
萎縮や変形がないかチェックできる
飼い主がよく抱く質問
初期症状が軽い場合でも病院に行くべきですか?
はい。早期であれば治療効果が高まり、進行を遅らせることが可能です。
高齢犬はどのくらいの頻度で検診を受ければよいですか?
年に2回以上の血液検査と尿検査が推奨されます。
健康な犬でもSDMA検査は必要ですか?
早期発見のために有効です。特にリスク犬種や高齢犬にはおすすめです。
まとめ
犬の腎臓病は初期症状が非常にわかりにくいため、飼い主の小さな気づきが早期発見につながります。
-
初期症状:多飲多尿、食欲不振、体重減少、口臭、元気低下
-
飼い主のチェック:飲水量・排尿量の記録、体重測定、食欲や口臭の観察
-
動物病院での検査:血液検査(BUN・クレアチニン・SDMA)、尿検査、画像診断
定期的な健康診断と日常の観察を組み合わせることで、腎臓病を早期に見つけ、愛犬の健康寿命を延ばすことができます。