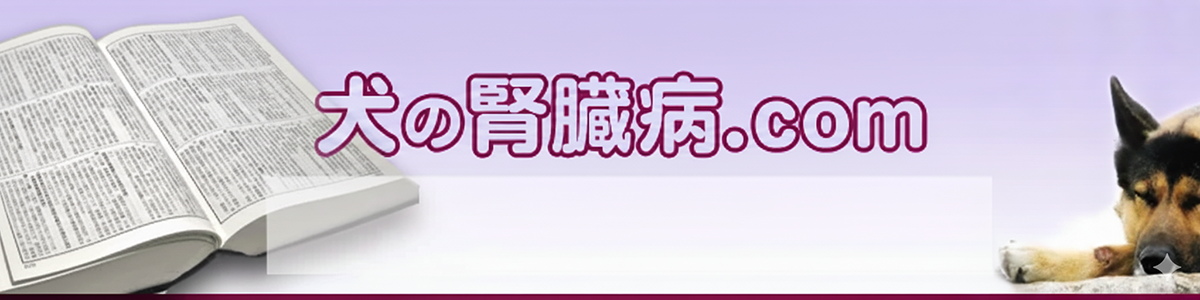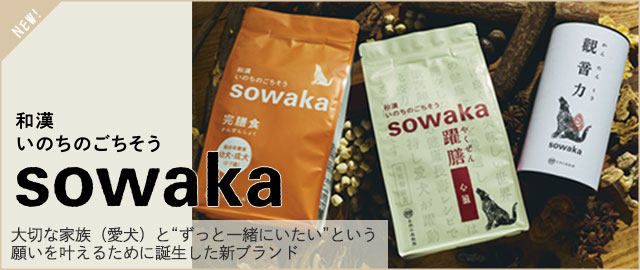犬の腎臓病は進行性であり、完治は難しい病気です。そのため治療の目的は、腎臓への負担を減らし、進行を遅らせ、生活の質を維持することにあります。食事療法や薬物療法と並んで重要なのが「点滴療法(輸液療法)」です。体内の水分や電解質のバランスを整え、毒素を排出しやすくするため、腎臓病の管理に欠かせない治療法といえます。
Contents
点滴療法(輸液療法)の目的
腎臓病になると、腎臓のろ過機能が低下し、体内の老廃物や余分な水分を適切に排出できなくなります。点滴療法は次のような目的で行われます。
-
脱水状態の改善
-
老廃物(尿素窒素・クレアチニンなど)の排出をサポート
-
電解質バランスの調整
-
吐き気や食欲不振などの症状緩和
-
全身状態の改善と生活の質の維持
点滴療法の種類
静脈点滴(IV輸液)
急性腎臓病や重度の慢性腎臓病で行われます。動物病院で入院し、24時間管理のもと静脈から点滴を行い、短期間で集中的に体内環境を改善します。
-
急性腎不全では命を救う治療となる場合もある
-
モニタリングが必要なため入院が前提
皮下点滴(皮下輸液)
慢性腎臓病の犬に広く行われる方法で、皮膚の下に補液を注入します。自宅で飼い主が行うケースも多く、通院負担を軽減できます。
-
数時間かけて体内に吸収される
-
自宅での継続治療に適している
-
脱水予防や老廃物排泄の補助として有効
点滴に使われる輸液の種類
腎臓病に使われる輸液は状態によって選択されます。
-
乳酸リンゲル液:一般的な補液
-
生理食塩水:電解質バランス調整に使用
-
電解質補正液:ナトリウム・カリウムなどを調整
-
ブドウ糖液:エネルギー補給や脱水補正に使用
輸液の種類や量は犬の体重・病態・検査結果に基づいて獣医師が決定します。
点滴療法のメリットとデメリット
メリット
-
体内の老廃物を効率的に排出できる
-
脱水を防ぎ、症状の緩和に役立つ
-
継続的に行うことで生活の質を維持できる
デメリット
-
通院または自宅点滴に飼い主の協力が必要
-
感染や注射部位の腫れなどのリスク
-
犬が嫌がることもあり、慣れるまで時間がかかる
自宅で行う皮下点滴の流れ
-
動物病院でやり方を習う
-
滅菌した輸液バッグと注射器を準備
-
首や背中の皮膚をつまみ、皮下に針を刺す
-
点滴が終わったら針を抜き、軽くマッサージする
初めは難しく感じるかもしれませんが、慣れると10〜20分程度で安全に行えるようになります。
飼い主がよく抱く質問
点滴は毎日必要ですか?
病気の進行度や症状によって頻度が異なります。軽度であれば週1〜2回、進行していれば毎日必要なこともあります。
自宅で皮下点滴をするのは安全ですか?
獣医師の指導を受ければ安全に行えます。初めは病院で練習し、少しずつ自宅でできるようになるケースが多いです。
点滴だけで腎臓病は治りますか?
点滴はあくまで腎臓病の進行を遅らせ、症状を緩和するための治療です。食事療法や薬物療法と併用することが不可欠です。
まとめ
点滴療法(輸液療法)は、犬の腎臓病治療における重要な柱の一つです。
-
静脈点滴は急性腎臓病や重症例に有効
-
皮下点滴は慢性腎臓病で自宅管理に適している
-
輸液の種類は病態に応じて調整される
-
食事療法・薬物療法と併用することで効果を最大化できる
飼い主が輸液の重要性を理解し、獣医師と連携して継続的に取り組むことが、愛犬の健康寿命を延ばす鍵となります。