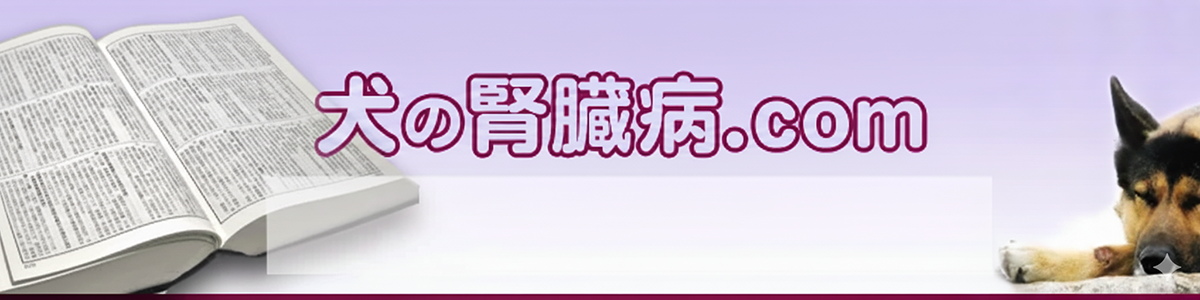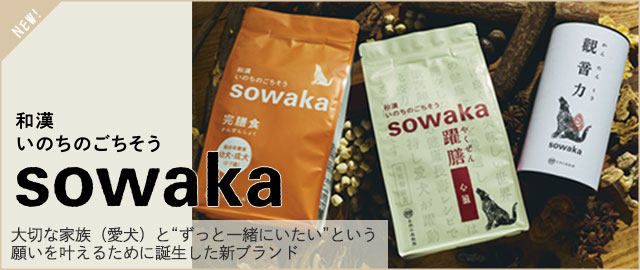犬の腎臓病は進行性であり、早期に発見することが難しい病気です。特に慢性腎臓病(CKD)はゆっくりと進行するため、飼い主が日常生活の中で異変に気づけるかどうかが大きな分かれ道になります。ここでは犬の腎臓病の代表的な症状から、初期症状・中期症状・末期症状までを詳しく解説し、飼い主がどの段階で気をつけるべきかを整理します。
Contents
腎臓病と症状の関係
腎臓は老廃物の排出と水分・電解質のバランス調整を担う重要な臓器です。この機能が低下すると体内に毒素がたまり、さまざまな症状が現れます。特に犬の腎臓病では、初期には目立った異常が出にくく、症状が出る頃には腎臓機能の大部分が失われていることもあります。
犬の腎臓病の初期症状
腎臓病の初期段階は「見逃されやすい変化」が特徴です。
-
多飲多尿:普段より水を多く飲み、尿量が増える
-
軽度の食欲不振:食べ残しが増える
-
体重の減少:ゆるやかに体重が減っていく
-
元気の低下:遊びや散歩への意欲が下がる
-
毛並みの悪化:ツヤがなくなる、パサつく
特に「多飲多尿」は腎臓病の代表的サインです。飼い主が水の減り具合や排尿の回数を観察することが重要です。
中期の症状
腎臓の機能低下が進むと、よりはっきりとした症状が現れます。
-
持続的な食欲不振
-
顕著な体重減少
-
嘔吐や下痢が続く
-
口臭がアンモニア臭を帯びる
-
脱水症状(皮膚をつまんでも元に戻りにくい)
-
無気力状態
血液中に老廃物(尿素窒素=BUN、クレアチニン)が溜まることで体に中毒症状が出てきます。
末期の症状
腎機能が大きく失われた末期では、命に関わる深刻な症状が見られます。
-
まったく食べなくなる
-
極度の体重減少と衰弱
-
頻繁な嘔吐・下痢
-
けいれんやふらつき
-
尿がほとんど出なくなる(乏尿・無尿)
-
重度の脱水と貧血
末期症状に至ると生活の質が大きく低下し、延命治療や緩和ケアが中心となります。
症状を見極めるためのポイント
飲水量と尿量の記録
健康な犬の1日の飲水量は体重1kgあたり約50ml程度です。体重10kgの犬で500mlを超えると「多飲」の可能性があります。
食欲や体重の変化を観察
「最近痩せた」「フードを残すことが増えた」と感じたら要注意です。
口臭・被毛・行動の変化
アンモニア臭を帯びた口臭、毛艶の悪化、動きの鈍さは腎臓病の兆候です。
腎臓病の症状と検査の関係
症状が出てから病院に行くと、すでに腎機能の多くが失われていることが多いのが腎臓病の怖い点です。症状と並行して次の検査が重要です。
-
血液検査:BUN、クレアチニン、SDMA
-
尿検査:尿比重、タンパク尿の有無
-
超音波検査:腎臓の形態変化
特にSDMAは早期発見に有効な新しい指標で、クレアチニンよりも早く腎機能低下を捉えることができます。
飼い主がよく抱く質問
腎臓病の症状が出たら手遅れですか?
手遅れではありませんが、症状が出ている段階で進行している可能性は高いです。進行を遅らせ、生活の質を保つことが大切です。
食欲不振があるが、必ず腎臓病ですか?
食欲不振は腎臓病以外の病気でも見られます。血液検査や尿検査で確認することが重要です。
初期症状を見分ける一番のポイントは?
水の飲み方と尿の量です。飼い主が日常的に記録しておくことで、異常の早期発見につながります。
まとめ
犬の腎臓病は初期段階では気づきにくいものの、日常の小さな変化を観察することで早期発見につなげることができます。
-
初期症状:多飲多尿、軽度の食欲不振、体重減少
-
中期症状:持続的な食欲不振、嘔吐、口臭、脱水
-
末期症状:食欲消失、無尿、極度の衰弱
症状が現れた時点で腎機能はかなり低下している場合も多いため、日頃から飲水量・排尿・体重を観察し、異変があれば早めに動物病院を受診することが愛犬の命を守る鍵となります。