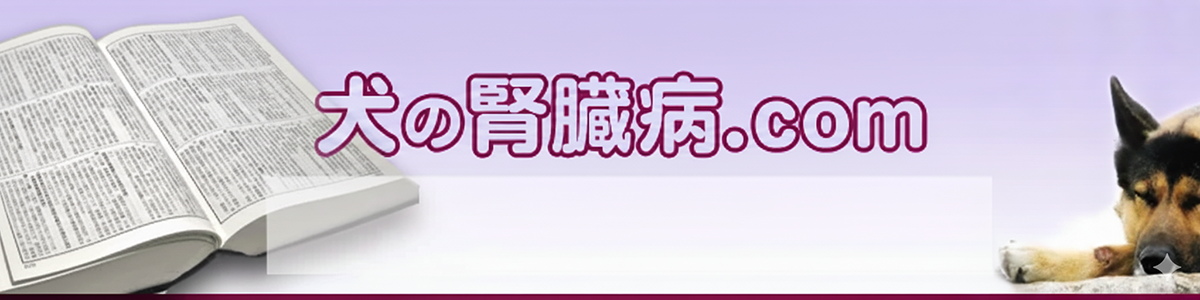犬のファンコニー症候群は、腎臓の尿細管に異常が生じ、本来再吸収されるべき栄養素やミネラルが尿中に漏れ出してしまう病気です。ブドウ糖やアミノ酸、重炭酸イオン、電解質などが体外へ失われるため、全身に深刻な影響を及ぼします。進行すると慢性腎不全に移行することもあり、特に早期発見と管理が重要です。ここでは犬のファンコニー症候群の原因、症状、検査、治療、そして飼い主ができるケアについて詳しく解説します。
Contents
ファンコニー症候群の原因
-
遺伝的要因
特にベーセンジー犬に多く発症することが知られている -
二次性要因
中毒(重金属、薬剤)、感染症、腫瘍、慢性腎疾患に伴うもの -
特発性(原因不明)
原因が明らかでないケースもある
症状
-
多飲多尿(大量に水を飲み、尿量が増える)
-
体重減少、痩せてくる
-
食欲不振
-
嘔吐や下痢
-
尿の異常(糖尿なのに血糖値は正常:腎性糖尿)
-
脱水や電解質異常による筋力低下やけいれん
-
慢性化すると腎不全の症状(貧血、口臭、倦怠感)が現れる
検査法
-
尿検査
糖尿の確認(血糖値は正常)、アミノ酸やタンパク質の排泄異常 -
血液検査
BUN、クレアチニン、SDMAで腎機能を評価
電解質異常(ナトリウム、カリウム、リンなど)を確認 -
遺伝子検査
ベーセンジー犬など遺伝的素因が疑われる場合に有効 -
画像検査
腎臓の形態や慢性腎疾患の有無を確認
治療法
支持療法
-
皮下輸液や点滴で脱水と電解質異常を補正
-
重炭酸ナトリウムで代謝性アシドーシスを改善
-
制吐剤や食欲増進剤で生活の質を高める
食事療法
-
腎臓病用療法食(低リン・低ナトリウム・適切なたんぱく質)
-
オメガ3脂肪酸や抗酸化成分を含むフードで腎臓保護
-
高嗜好性のウェットフードやトッピングで食欲維持
薬物療法
-
必要に応じて降圧薬や抗酸化剤を併用
-
血栓症予防として抗血小板薬を使用する場合もある
合併症と予後
-
慢性腎不全への進行リスク
-
電解質異常による心不全やけいれん
-
骨軟化症(カルシウム・リン代謝異常による骨の脆弱化)
-
適切に管理すれば長期生存も可能だが、重度の場合は予後不良となることもある
飼い主ができるケア
-
定期的な血液・尿検査で腎機能と電解質をチェック
-
新鮮な水を常に用意し、脱水を防ぐ
-
療法食を継続し、嗜好性の工夫をして食欲を保つ
-
体重や排尿量の変化を毎日観察
-
嘔吐や元気消失が見られたらすぐに受診
飼い主がよく抱く質問
ファンコニー症候群は治りますか?
根治は難しく、生涯管理が必要です。ただし早期に発見し、適切な治療を行えば長期的に安定した生活が可能です。
糖尿とどう違うのですか?
糖尿病では血糖値が高くなるのに対し、ファンコニー症候群では血糖値が正常でも尿に糖が出るのが特徴です。
遺伝性の場合、予防できますか?
遺伝性は予防が難しいため、発症リスクがある犬種では定期検診が重要です。
まとめ
犬のファンコニー症候群は、腎臓の尿細管障害によってブドウ糖やアミノ酸などが尿に漏れ出す病気です。
-
主な原因は遺伝性、感染症、中毒、慢性腎疾患など
-
症状は多飲多尿、体重減少、食欲不振、脱水、電解質異常など
-
治療は支持療法、食事療法、薬物療法を組み合わせて行う
-
合併症を防ぐため定期検診と日常管理が不可欠
飼い主が日常観察を徹底し、獣医師と連携して管理することで、愛犬の生活の質を守ることができます。